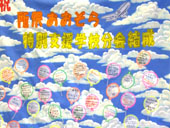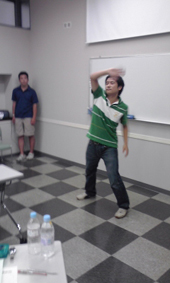障教部の活動 更新日2013.7.7 |
■2013年6月8日(土)障害児教育部定期大会
|
■2013年5月11日(土)新歓学習会
|
■2013年4月27日(土)新歓バレーボール大会
|
■第12回全国障害児学級&学校学習交流集会学習交流集会は1100人以上の参加者があり、大成功を収めました。埼玉の障害児学校からは350名以上の参加がありました。
|
| ■2012年7月21日(土)夏の組合学校を開催しました。定期大会で実施した教育課程、コーディネーターや地域支援、臨任者などの実態調査の報告、全国障害児学級&学校学習交流集会の取り組み、分会活動の交流などを行いました。 |
■2012年5月12日(土)新歓学習会として、三木裕和さん(鳥取大学)を迎え、(仲間の中で 子どもと育つ教師」という演題の講演会を開催しました。若者を中心に100名が参加しました。
|
| ■2012年2月11日(土)第31回埼玉障害児教育研究集会を埼教組、教育文化研究所障害児教育研究委員会と共催で行いました。午前中の全体会(妹尾さんの記念講演など)には約70名、午後の分科会とあわせると約100名の参加がありました。 |
| ■2011年12月3日(土)分会代表者会議に続き、第3回連続セミナーが開催されました。約20名の参加があり、性教育と卒業後の生活について学びました。 |
| ■2011年11月13日(日)入間向陽高校を会場に「教育のつどい2011」の分科会が開催されます。障教部では「障害をもつ子の教育」分科会の運営委員や世話人などで協力します。 |
| ■2011年11月3日(文化の日)埼教組障教部と共催で「障害児教育フェスタ2011」を開催しました。ワークショップなどの8講座と教材展示コーナーや栄養職員部の試食や実践紹介、書籍販売など多彩な企画でした。70名の参加者を集めることができました。 |
| ■2011年10月16日埼玉県障害者交流センターを会場に障害者まつり(主催堂実行委員会)が開催されました。障教部では栄養職員部、寄宿舎委員会と協力して展示・試食会の企画で参加しました。また、各分会からの多数の要員を出してまつり成功を支えました。 |
| ■2011年10月1日(土)第2回障害児教育連続セミナーが開催されました。今回は障害当事者である高橋琴枝さんのあゆみから学ぶミニ学習会と青年教員の前田さんを講師とした「知的障害」の学校の小学部の授業づくりの講座が行われました。参加者からの疑問や悩みをもとにした交流も好評でした。 |
| ■2011年9月3日(土)障害児教育連続セミナー2011がスタートしました。第1回目は小出信之さんを講師とした病弱教育についてのミニ学習会と佐竹葉子さんを講師とした「肢体不自由児」の学校での授業づくりについて学びました。 |
| ■2011年8月18日障埼連主催の“障害児教育充実重点要求”交渉が行われました。小児医療センターの移転に伴って、岩槻特別支援学校の教育が継続するように、教室不足の抜本的解決のために新たな学校の建設などを訴えました。父母も含めて100名以上の参加がありました。 |
| ■2011年6月11日(土)埼玉教育会館を会場に第56回障害児教育部定期大会が開催されました。 |
| ■2011年4月29日のバレーボール大会は諸事情により、延期(日程未定)となりました。 |
| ■2011年2月19日第30回埼玉障害児研究集会が開催されました。 記念講演は船橋秀彦さん(茨城県立特別支援学校教諭)による「育てあう力を育てる−キャリア教育をのりこえて、真の自立を育てる教育」が行われました。午後は分科会で実践を深めあいました。約100名の参加がありました。 |
■2010年12月4日(土)授業づくり連続セミナー2001の第3回は映画『夜明け前の子どもたち」と中村尚子さんによる特別講演「映画から学ぶ障害児の人権保障の歴史」でした。役員を含めて30名の方が参加し、1960年代の重症心身障害児療育施設「びわこ学園」での実践を学びました。 |
■2010年5月15日(土)佐藤比呂二さんを講師に迎え、「子どものほんとうのねがいをつかむ」という演題で、新歓学習会が開催あれました。会場の見沼グリーンセンターでは、マイクがつかえないというハプニングもありましたが、約90名の参加者が熱心に話を聞いて学習しました。全障研埼玉支部でも宣伝してくれたおかげで教員以外の参加者もありました。 |
■2010年4月29日、加須市騎西総合体育館ふじアリーナを会場に障教部バレーボール大会が開催されました。優勝は狭山特別支援学校分会でした。 |
■2010年4月1日、新設校「所沢あおぞら特別支援学校」に分会が結成されました。障教部の各分会からは寄せ書きのタペストリーを送りました。 |
■2009年12月25日(金)埼玉県教育局と埼高教障害児教育部。埼教組障教部との交渉が行われました。保護者も含めて120名が参加し、学校増設や定数改善、医療的ケアの充実など切実な要求を訴えました。 |
■2009年12月5日(土)第3回障害児教育連続セミナーが開催されました。今回は医療的ケアのミニ学習会と栄養職員さんを講師とした「食教育」の授業の講座が行われました。 |
■2009年11月15日鷲宮高校を会場に「教育のつどい2009埼玉集会」の分科会が開催されました。「障害をもつ子どもの教育」分科会では6本のレポートが報告され、討論が行われました。 |
■2009年11月3日(文化の日)障害児教育フェスタ2009が開催されました。5つの講座には多くの若者を含む80名の参加者がありました。また、教材展示コーナーでは各学校からの教材胸部や栄養職員部の給食や食育の資料展示、寄宿舎委員会からは寄宿舎を紹介する掲示がありました。 |
■2009年10月3日《土)第2回障害児教育部連続セミナーが開催されました。岩槻特別支援学校の田中さんが病弱教育について紹介してくれました。病棟に持って行って子どもたちとやっているゲームも紹介してくれました。ワークショップは浦和特別支援学校の山森さんによる「サンバ」。楽器ごとのリズムを練習した後に、みんなであわせて演奏しました。 |
■2009年8月29日(土)障教部連続セミナー09がスタートしました。第1回めは障害者自立支援法訴訟をたたかう新井さんが保護者の立場で子どもさんの育ち屋思いを語ってくれました。また聴覚障害をもつろう学校教員の戸田さんから自身の育ちをふまえてろう教育の歴史と教育実践が語られました。 |
|
|
■障害児教育部夏の組合学校は7月19日(日)に開催されました。分会代表者会議に続き、全教障教部事務局長の土方さん、前全教委員長の米裏さんを講師に迎えた学習会を行いました。会場が満席になるほど盛況でした。 |
■2009年6月7日(日)第54回障害児児教育部定期大会が開催されました。 |
■2009年5月9日(土)全障研埼玉支部・さいたま市教組障教部・埼高教障教部の共催で三木裕和氏(兵庫県立出石特別支援学校教諭)を講師に「新歓講座 人間を大切にするしごと」を開催しました。約130名の参加があり会場はほぼ満席となりました。(この内県立の障害児学校からは約60名。県外の学校からの参加もありました。) |
■2009年4月29日(水・祝日)第28回障教部バレーボール大会を鴻巣総合体育館で開催しました。前日に歓送迎会を行った学校もある中、全県の障害児学校17校から17チームが参加しました。一つの職場から複数のチームが出場したところやいくつかの職場で合同チームをつくって出場したところなどもありました。応援での参加者なども入れると170名が参加し、大変盛り上がりました。今回の優勝は川島ひばりが丘養護学校でした。決勝リーグは常連のチームですが、今回が初優勝です。 |
| ■09年3月27日、埼玉県議会は多くの障害当事者、生徒、教職員、関係者の反対や危惧を押し切って盲、ろう、養護学校の名称を「特別支援学校」に変更する学校設置条例を可決・成立させました。 たくさんの県議の方に反対運動を支援していただきましたが、結果的に本会議で反対した議員は共産党と社民党の議員の方だけでした。残念な内容でしたが、これで終わるわけではありません。埼高教としては、引き続き関係者と力を合わせ、障害種別の教育の専門性を守るといわせたことをはじめ、障害児教育のリストラ・解体を許さず、充実・発展の立場で奮闘します。 |
■09年2月21日(土)午前 埼玉障害児教育研究集会(埼教組障害児教育部・埼高教障害児教育部・さいたま教育文化研究所障害児教育研究委員会 共催)が開催され、特別報告(講師:土方 功さん)と記念講演(講師:妹尾豊広さん)の全体会に60名が参加しました。 |
■09年2月14日(土) 「埼玉の寄宿舎教育を語るつどい」が開催されました。清田さんによる記念講演とシンポジウムには、他県からの参加者を含む50名の参加がありました。 |
■09年1月17日(土) 授業づくり連続セミナー第4回が開催されました。ミニ学習会では訪問教育の歴史と実践を学び、絵本や人形などたくさんの教具を見せてもらい、各自が授業実践のイメージをふくらませました。また、民舞のDVDの紹介もありました |
■09年01月10日から12日、東京を会場に全国障害児学級&学校学習交流集会が開催されました。10日は中野ZEROで全体会が開催されました。構成劇は養護学校義務制に5年先駆けて希望者全入を実現させた運動を振り返り、石原都政の下でかけられている攻撃を告発し、反転攻勢していこうという意気込みを感じるものでした。たくさんの若者がステージ狭しと踊り、希望を語る場面は圧巻でした。 |
■08年12月26日(金)埼玉県高等学校教職員組合障害児教育部・埼玉県教職員組合障害児教育部は体験交渉をおこないました。保護者も含め150人の参加があり、学校増設をはじめとする教育条件整備についての切実な要求を訴えました。 |
■寄宿舎委員会では09年2月14日に「埼玉の寄宿舎教育を語るつどい」を開催します。 |
■08年12月06日(土)08年授業づくり連続セミナー第3回目が開催されました。 |
■08年12月3日(水)校名変更問題に関する要求書を元に特別支援教育課との交渉をおこない、生徒や卒業生など障害当事者をはじめとする関係者の意見をよく聞いて拙速に変更しないようにと訴えました。 |
■08年11月25日(火)文化祭の代休を利用して、県議会各派(自民党、民主党、公明党、刷新の会、共産党、社民党)に12月県議会に提出するすべての障害児にゆきとどいたいた教育を求める」陳情書への協力を求める行動をおこないました。 |
■08年10月25日(土)障害児教育フェスタ2008を開催しました。展示は普段使っている教材の展示や栄養職員部による学校給食の展示、講座は和太鼓やパネルシアター、口頭作文の実践、発達講座などでした。約60名の参加者がありました。 |
■08年8月30日(土)08年授業づくり連続セミナー第1回目がスタートしました。若い教職員が参加し、埼玉における発達障害児教育の歴史や課題、障害の重い子の授業づくりについて学びました。 |
■08月19日(火)障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会(障埼連)の体験交渉がおこなわれました。埼高教障害児教育部の各分会は保護者とともに切実な要求を訴えました。 |
| ■06月07日(土)障害児教育部定期大会を開催し、今年度の活動方針を決定しました。 |
■ 障教部では今年秋から冬にかけて青年を対象とした授業づくり連続学習会を開催します。ただいま参加者を募集しています。詳しくは「学習会・研究集会情報」のビラをご覧下さい。 |
| ■ 08年06月01日(日)障害児教育部分会代表者会議を開催しました。分会活動の交流や06月07日(土)に開催される定期大会の議案説明などを行いました。 |
|
■ 08年02月16日(土)に埼高教障教部・埼教組障教部・さいたま教育文化研究所障害児教育研究委員会の共催で開催された「第27回埼玉障害児教育研究集会」のまとめができました。(PDFファイルを「リーフ・討議資料」に載せました。) |
■ 05月17日(土)新歓学習会が開催され、70名が参加しました。「自閉症児が変わるとき」というテーマで、佐藤比呂二さんが実践を通して、自閉の子どもに限らず子どものとらえ方を語ってくれました。障害からだけでなく、発達的にも子どもをとらえることの重要性、自閉症の子どもは人との関係が苦手だけど人との関係を求めていること、自分で選択する力を育てること、自己肯定感を育ってることの重要性など、大切なことをたくさん学びました。 |
■ 今年も4月29日に鴻巣市民体育館を会場に障教部バレーボール大会を開催しました。 |
| ■08年度障教部新歓学習会は05月17日(土)13:30〜16:30、埼玉県障害者交流センターを会場に開催されます。 佐藤比呂二さんを講師に迎えます。自閉症の子どもへの実践を通して、子どもの心に寄りそうことを学びませんか。楽しいパフォーマンスにもご期待下さい。職場の仲間を誘ってご参加下さい。ビラはこちら(PDF)。 |
| ■08年度バレーボール大会(4月29日、鴻巣体育館)のビラ(PDF)ができました。 なお、今回は会場がいつもの北本体育館から鴻巣体育館に変わっていますのでご注意下さい。 |
| ■08年3月23日(日)に障教部春の組合学校・08年度第1回分会代表者会議を開催します。新旧の分会役員の方の参加をお願いします。 |
| ■08年1月30日 07年11月11日に川越女子高校を会場に開催した「教育のつどい西ブロックフォーラム」(高校の特別支援教育をテーマとしたフォーラム)のまとめができたました。(PDF) |
■1月26日(土)に障害児教育部の分会代表者会議を開催します。 |
2008年01月12日〜14日 ■全国障害児学級・学校学習交流集会in岡山には全国から782人が参加しました。埼高教障害児教育部からも9名(全教役員4名を除く)が参加しました。 |
2007年12月25日 10:00〜12:00 ■ 埼高教障教部と埼教組障教部は県教育局との交渉を行いました。
|
■ 埼教組障教部・埼高教障教部・さいたま教育文化研究所障害児教育研究委員会は08年2月16日(土)に第27回障害児教育研究集会を開催します。 |
| ■ 11/19、26 障害児教育充実要請行動を行いました。19日は浦和駅及び郵便局前での街頭署名行動、26日は県議会各派への要請行動を行いました。 |
2007年11月03日 ■ 障害児教育フェスタ2007 を開催しました。 |
2007年06月09日 ■ 障教部定期大会がありました。 |
2007年04月30日 ■ 障教部は04月30日に今年も北本体育館で障教部バレーボール大会を開催しました。さいたま桜高等学園を含む22分会14チーム150人が参加し、熱戦を繰り広げました。 |
2007年4月1日 ■ さいたま桜学園と羽生ふじ学園が開校し、開校と同時にそれぞれ分会が結成されました。障教部分会代表者会議では分会結成を祝って他分会からのメッセージの寄せ書きのタペストリーを送りました。 |
2007年3月25日 ■ 障害児教育部の有志で全教委員長に就任する 埼高教米浦正委員長(元 坂戸ろう学校、元 大宮ろう学校)を励ます会を開催しました。 |
2007年2月17日 ■ 第26回埼玉障害児教育研究集会で、埼高教障教部と埼教組障教部では、4月からの特別支援教育の本格実施を前に、私たちの望む今後の障害児教育・「特別支援教育」の方向性についての提言リーフを発表しました。 |
2007年1月6〜8日 ■ 全教および教組共闘の主催で「全国障害児学級・学校学習交流集会」が京都で開催され、埼高教障害児教育部からは34名が参加しました。 |
2006年12月26日 ■ 埼高教障教部と埼教組障教部は父母とともに県教育委員会との交渉を行いました。 |
|
2006年11月20日、27日 ■ 障教部では文化祭などの代休を利用して、保護者とともに県議会各派に対して要求要請行動を行いました。 |
|
2006年10月28日(土) ■ 障害児教育フェスタ2006を開催しました。今年度は栄養職員部の参加もあり、70名以上が参加しました。 |
|
2006年9月2日(土) ■ 障害児教育部夏の組合学校を開催しました。 |
|
2006年8月20日(日) ■ 「つながろう! 今、みんな輝け! わたしが、ぼくが主人公」をテーマに、特別支援教育フォーラムが埼玉会館小ホールで開催され、障害児学級、盲・ろう・養護学校の卒業生や高等部の生徒達のリレートーク、保護者や通常学級の教員、定時制高校の教員によるシンポジウムがおこなわれました。約500名が参加しました。 |
|
2006年8月19日(土) ■ 教育のつどい2006(全国教育研究集会)の障害児教育分科会の交流会が開催されました。約60名が参加し、大変盛り上がりました。 |
|
2006年8月7日(月) ■ 障埼連(障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡会、埼高教も加入)の教育分野の対県交渉が行われました。 |
|
2006年07年02日(日) ■ 埼高教、埼教組、埼玉私教連などによる「未来をひらく教育のつどい2006」実行委員会、および「同西部実行委員会」による「特別支援教育を考える教育フォーラム」は川越市民会館を会場に基調講演(大和久勝氏)とシンポジウムからなるフォーラムを開催しました。 |
|
2006年06月10日(土) ■ 障害児教育部51回定期大会が開催されました。29分会すべてから66人の代議員の参加がありました。 |
|
2006年5月13日 ■ 障教部では新歓学習会を開催しました。茨城県立土浦養護学校の森下芳郎氏を招いて「障害児学校の授業づくり」について講演をしていただきました。青年教職員と昔の青年教職員を含め30名の参加がありました。 |
|
2006年4月1日 ■ 埼高教障教部と埼教組障教部は共催で、さいたま市民会館・浦和を開場に、「保護者・教職員・関係者の緊急学習会 学校教育法の「改正」でどうなる? 障害児教育」を開催しました。 |